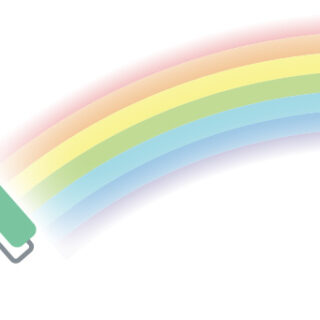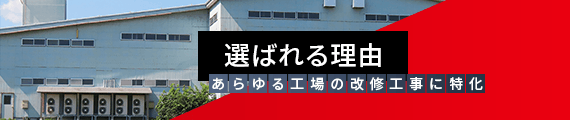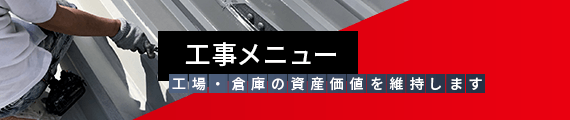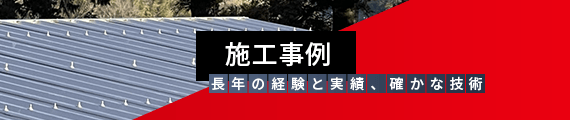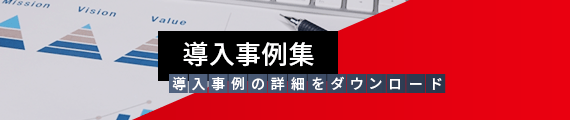外壁にうっすらと茶色いスジが…。それ、「錆汁」かもしれません。原因とリスク、そしてプロによる補修方法

外壁に現れるうっすらとした茶色いスジ。
雨の跡のようにも見えますが、雑巾で拭いても落ちない——そんな場合は「錆汁(さびじる)」が発生している可能性があります。
錆汁は、外壁の内部で金属部材が腐食し、その錆が雨水などとともに表面へ染み出してきた状態を指します。
見た目の問題にとどまらず、建物内部の劣化が進行しているサインでもあり、早期発見・早期対応がとても重要です。
この記事では、錆汁の原因と放置した場合のリスク、そして専門業者による補修・再発防止の方法について解説します。

■ 錆汁とは?発生の仕組み
錆汁は、金属部材が酸化して生じる錆が、水分に溶け出して外壁表面に染み出す現象です。
鉄分を含んだ水が外壁をつたい、乾いたあとに茶色い筋やシミとなって残ります。
発生源となる金属部材は、主に次のようなものです。
- 鉄筋コンクリート内部の鉄筋
- 外壁下地や庇(ひさし)に使用される鉄骨部材
- 手すりや笠木の金物固定部
- サッシ周りのアンカー金具やビス
これらの金属が雨水や湿気によって酸化(錆化)し、その錆がコンクリートやモルタルを通してにじみ出すことで、
外壁表面に“錆汁”として現れます。


■ 錆汁が発生する主な原因
錆汁の原因は、単に「金属が錆びた」だけではありません。
そこには水分の侵入経路や防錆・防水施工の劣化といった複合的な要因が関わっています。
① ひび割れ(クラック)からの雨水侵入
モルタルやコンクリートの微細なひび割れは、雨水の浸入経路となります。
特にヘアークラックと呼ばれる細い亀裂でも、長年の経過で鉄筋部まで水が達し、錆びを発生させます。
② シーリングの劣化
サッシ周りや外壁目地のシーリング材が経年劣化し、剥離・亀裂が生じると、そこからも水が侵入します。
内部のアンカー金具などが錆び、錆汁として外に流れ出すケースは非常に多いです。
③ 金属部材の未防錆処理・塗膜の剥がれ
建築時に防錆塗装が十分でなかったり、経年で塗膜が剥離していると、鉄部が直接湿気や雨水に触れて錆が発生します。
④ 結露や内部漏水
屋内側での結露や配管からの漏水などが、壁体内部を湿らせ、結果的に錆汁が外壁側に現れることもあります。
■ 放置するとどうなる?錆汁が示す“見えない劣化”
錆汁は「外壁の汚れ」として軽視されがちですが、構造上の劣化が進んでいる可能性を示す警告サインです。

1.鉄筋コンクリートの中性化・鉄筋腐食の進行
コンクリート内部の鉄筋が錆びると、鉄は体積が約2〜4倍に膨張します。
この膨張圧によってコンクリートが内部から押し割られ、剥離・爆裂が発生。
最終的には躯体の耐久性が著しく低下します。
2.外壁タイルの浮き・剥落
タイル貼り仕上げの建物では、下地のモルタルが錆の膨張圧によって浮き上がり、タイルの剥落事故につながるケースも。
居住者や通行人への落下リスクを伴うため、管理責任の観点からも無視できません。
3.漏水・雨漏りの原因に
錆汁が出るということは、すでに水分が内部へ侵入している状態です。
放置すれば、室内への雨漏りや内装仕上げ材の汚損へと発展します。
■ プロが行う調査と補修の流れ
錆汁が確認された場合、まずは原因を正確に特定することが重要です。
見た目だけを洗浄しても、内部の錆が残っていればすぐに再発します。
① 現地調査
専門業者は、目視・打診・含水率測定などを行い、錆汁の発生位置や範囲を確認します。
必要に応じて赤外線サーモグラフィーや中性化試験を行い、内部の腐食状況を把握します。

② 下地補修
原因箇所を特定したら、錆が発生している下地を部分的に斫(はつ)り、鉄筋や金物を露出させます。
そのうえで次の工程に進みます。
③ 錆の除去・防錆処理
ワイヤーブラシやサンドブラストなどで錆をしっかり除去し、防錆材を塗布します。
使用される防錆材はエポキシ樹脂系や無機ジンク系など、環境条件と下地の種類に合わせて選定されます。
④ 断面修復
モルタルやポリマーセメント系材料で断面を復旧し、周囲との平滑性を整えます。
コンクリートの中性化防止のために、仕上げには防水性・透湿性のある下地材を使用することが一般的です。
⑤ 表面仕上げ・再塗装
最後に、既存仕上げに合わせた塗装やタイル補修を行い、外観を整えます。
塗装仕上げの場合は、防水機能付きの高耐久塗料を選ぶことで再発を抑制できます。
■ 錆汁の再発を防ぐためのポイント
1.定期点検を実施する
外壁の劣化は年単位で進行します。
5年ごとの簡易点検、10〜12年ごとの大規模修繕を目安に計画的に実施しましょう。
2.シーリングや塗膜の寿命管理を行う
シーリング材の耐用年数は10年前後。
劣化が始まる前に打ち替えを行うことで、水の侵入を防げます。
3.雨仕舞(あまじまい)の見直し
庇や笠木、配管まわりなど、水が溜まりやすい部分の構造を改善し、再発リスクを低減します。
4.防錆塗装や防水トップコートを採用する
金属部には定期的な防錆塗装を、コンクリート部には防水トップコートを施すことで、
内部への水分侵入を防ぎます。

■ まとめ:錆汁は「見えない劣化」のサイン。早めの調査が鉄則
外壁に茶色いスジが現れたら、それは「錆汁」という建物のSOSかもしれません。
見た目の問題だけでなく、内部では鉄筋の腐食やコンクリートの劣化が進んでいる可能性があります。
放置すれば、構造体の損傷、タイル剥落、雨漏りといった二次被害を引き起こすため、専門業者による早期点検と補修が欠かせません。