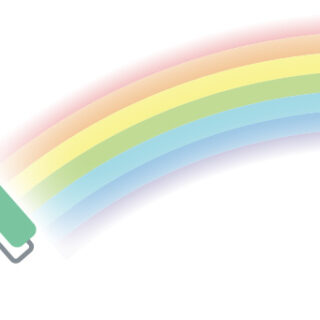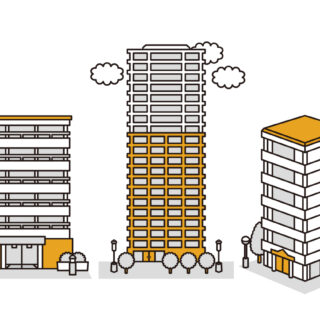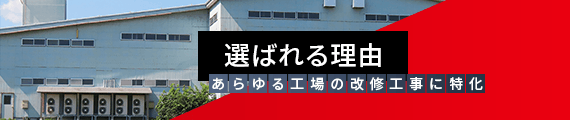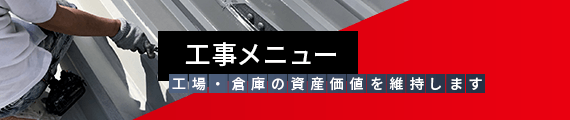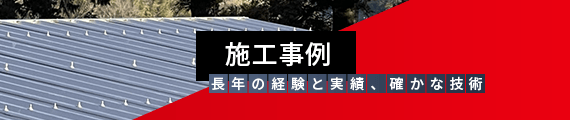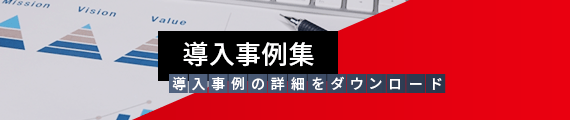塗装塗膜のシチュエーション別の劣化から知る補修時期
〜見逃すと危険!劣化サインから適切なメンテナンスを見極める〜
塗装された建物や設備は、年数の経過や環境の影響により徐々に劣化します。しかし、塗膜の劣化は一様ではなく、建物の立地条件や使用用途によって劣化のパターンもスピードも異なります。今回はシチュエーション別に見られる塗装塗膜の劣化と、補修の適切なタイミングについてご紹介します。
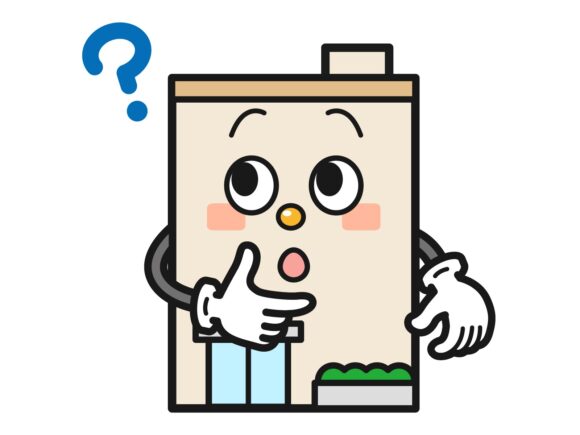
1. 海沿いエリアの建物
海が近いエリアにある建物は、景観や利便性に優れる反面、過酷な自然環境によるダメージも避けて通れません。
ここでは、海沿いの「マンション」「工場」「倉庫」それぞれの特徴と、必要なメンテナンスや改修の注意点をわかりやすく解説します。
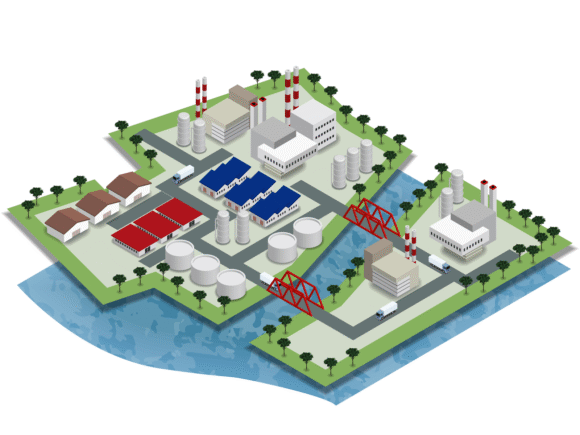
◆ 海沿いエリアに建てるメリット
|
建物 |
主なメリット |
|
マンション |
・海が見える立地で資産価値が高くなる |
|
工場 |
・港湾インフラに近く物流に強い |
|
倉庫 |
・港湾業務と連携しやすい |
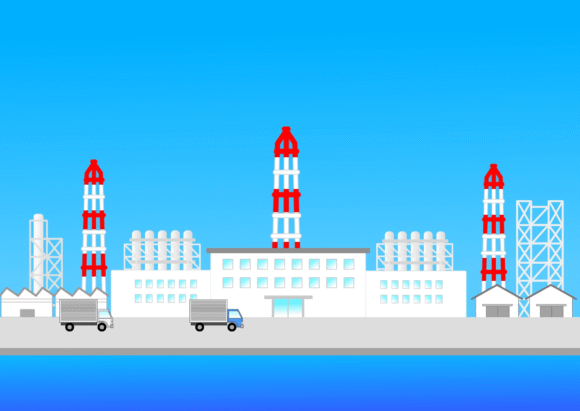
◆ 一方でデメリットは…?
■ 塩害(海から吹き付ける潮風などの塩分を含む風や飛沫)の影響を受けやすい
海からの距離や風向きなどにより状況も異なりますが、海から1キロメートルくらいまでは、塩害の影響がある地域もあります。
具体的な塩害の影響
- 金属部材のサビや腐食が早い
- 外壁や屋根の塗膜が劣化しやすい
- エアコンや換気設備の寿命が短くなることも
■ 雨風・台風の影響が大きい
海が目前、一望出来るような場所では、遮るようなものが無い為に海から吹き付ける風の影響を強く受けることになります。
具体的な影響
- 建材の摩耗が加速
- 台風時の塩水混じりの雨で壁やガラスが汚れやすい
■ 湿度・結露のリスク
海が近いため、空気に水分がふくまれやすい環境になります。
具体的な影響
- 潮風や気温差により、建物内部での結露発生率が高まる
- カビ・藻の繁殖や断熱材の性能低下につながることも
◆ マンションのメンテナンス・改修ポイント
- 外壁タイルやシーリング材の劣化点検を定期的に
- 共用部の鉄部(階段・手すりなど)は防錆塗装を強化
- バルコニーや屋上の防水層を高耐久仕様にするのが効果的
✨【ポイント】
塩害に強いシリコン・フッ素系塗料や、金属部には防錆下塗り+トップコートの2層仕上げを推奨!
◆ 工場・倉庫のメンテナンス・改修ポイント
- 折板屋根や鉄骨フレームのサビ対策は最優先
- 外装パネルやシャッター部の防錆塗装も要確認
- 高所・見えない箇所の定期点検を怠らない
🚧【改修時の注意】
生産ラインを止めずに補修したい場合は、夜間・休日施工や部分ごとの計画改修が可能な業者を選定しましょう。
◆ 海沿いエリアでは“通常より短い周期”での点検・補修が必須!
海沿いは見た目以上に過酷な環境。
一般的な建物よりも、3〜5年早いサイクルでの点検・塗装・補修が理想です。
|
項目 |
一般エリア |
海沿いエリア |
|
屋根・外壁塗装 |
約10年 |
約5〜7年 |
|
防水工事 |
約10〜15年 |
約7〜10年 |
|
鉄部メンテ |
約5〜7年 |
約3〜5年 |
景観と機能を両立するには、計画的な維持管理がカギ!
海沿いのマンションや工場・倉庫は、見た目や立地の魅力と引き換えに、耐候性への配慮が重要です。
塗装や防水といった外装のメンテナンスはもちろん、設備機器の耐塩害仕様の採用や、施工業者との継続的なパートナーシップが資産価値を保つポイントになります。
☑ ご相談ください
「塩害に強い塗料は?」「台風被害を減らしたい」など、
現地調査〜提案・見積もりは無料対応可能です。
お気軽にご連絡ください。
2.工場・倉庫、マンションの大きな面積を持つ屋根
工場や倉庫、マンションといった大型建築物の屋根は、日々厳しい自然環境にさらされています。
太陽の紫外線、風雨、排気ガス、潮風などの影響を受ける塗膜は、時間の経過とともに確実に劣化していきます
工場やマンションで使われる屋根の種類
- 陸屋根:
傾斜のない平面状の屋根で、ビルやマンションなどの高層建築物に多く見られます。
- 折板屋根:
金属製の屋根で、工場や倉庫などの大規模建築物に適しています。高い防水性と耐久性を持ちます。
- 瓦棒葺き:
金属製の屋根で、工場や倉庫などで広く使われています。
- 波型スレート屋根:
セメントを主な素材とする屋根で、耐久性、遮熱性、耐火性、遮音性が高いのが特徴です。
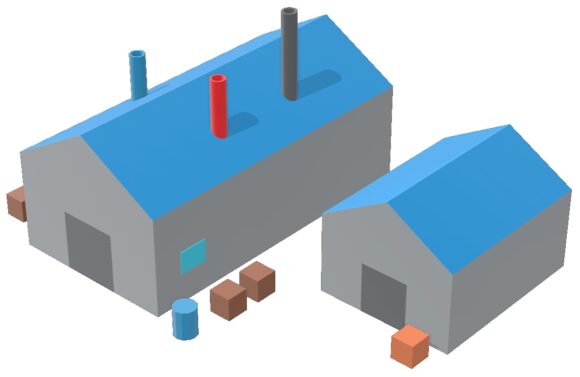
■ なぜ屋根塗装の「劣化」を見逃してはいけないのか?
塗膜は単なる色付けではなく、建物を守る“防護膜”です。
とくに屋根は、雨水や紫外線を真っ先に受けるため、塗膜が劣化すると雨漏りや錆の原因になります。
そのまま放置すると、補修では済まず、全面張り替えなど大規模な工事が必要になるケースも。
■ 塗膜劣化の主な症状と目安時期
|
劣化症状 |
内容 |
補修の目安 |
|
ツヤ引け |
表面の光沢がなくなる |
築5〜7年程度 |
|
変色・退色 |
色があせ、ムラが出る |
築7〜10年程度 |
|
チョーキング現象 |
表面を手で触ると白い粉がつく |
補修サイン:早期対応で塗り替え可能 |
|
ひび割れ・塗膜の剥がれ |
塗膜の機能が失われている |
緊急性高:下地補修も必要 |
|
サビの発生(鉄部) |
腐食の始まり |
放置厳禁:母材にダメージ進行 |
■ 補修時期の見極めポイント
塗膜の劣化は、外観の変化から早期に気づけることが多いです。
以下のような変化が見られたら、専門業者による調査をおすすめします。
- 雨上がりに屋根表面がいつまでも濡れている
- 塗装面に白い粉(チョーキング)が出ている
- 屋根板金の継ぎ目にサビや浮きがある
- 鳩小屋、塔屋などの突起部分の塗膜が剥げている
■ 屋根の大きい建物特有の注意点
- 面積が広いため劣化が一気に広がる
一部の劣化から全体へ広がるスピードが早く、部分補修が効きにくくなるケースがあります。
- 高所・傾斜・構造の複雑さ
足場や仮設が必要なケースが多く、工期・費用も規模が大きくなりやすいです。
- 立地条件(海沿い・工業地帯など)で耐用年数が短くなる
塩害や排気ガスによって、塗膜の耐用年数は数年単位で短くなることもあります。
■ 定期点検と早期対応がコスト削減に
塗装は“外観美化”だけでなく、建物寿命を守る保全工事です。
とくに大型建築物では、計画的なメンテナンスと点検が大きな修繕費の抑制につながります。
以下のようなタイミングで専門業者にご相談ください:
- 築10年前後(または前回塗装から10年)
- 塗膜の変色やサビが目立つようになった
- 定期点検報告で塗膜の劣化が指摘された
■ まとめ
塗膜の劣化を見逃さず、正しいタイミングでの補修・再塗装を行うことで、
建物の機能と資産価値を長く維持することができます。
放置はリスクを拡大させるだけ。
まずは現状の塗膜状態を知るために、無料調査や診断を依頼してみてはいかがでしょうか?
3. 日陰の壁面や北側
― 日陰の壁面や北側の注意点 ―
建物の塗膜は、太陽光や雨風といった外的要因によって徐々に劣化していきます。
しかし、日当たりの悪い北側の壁面や常に日陰になる場所では、
一見劣化が進んでいないように見えても、**見えにくい“別のリスク”**が潜んでいます。


■ 日陰・北側特有の塗膜劣化とは?
・カビ・コケ・藻の発生
直射日光が当たらないため、壁面が常に湿気を含みやすい状態になります。
このような環境では、カビ・コケ・藻が繁殖しやすく、見た目だけでなく塗膜や外壁材自体を傷める原因になります。
・塗膜の軟化・剥がれ
湿気が多い環境では、塗膜が水分を吸収して膨らみ、柔らかくなることがあります。
それが原因で塗膜が部分的に浮いたり、ひび割れたり、剥がれたりすることも。
・結露による内側からの劣化
特に鉄骨系の倉庫や工場では、外気との温度差で内外結露が発生し、
塗膜の下に水分が入り込むことで、見た目では気づきにくい腐食が進行している場合もあります。
■ 目に見えるサインに注意
以下のような兆候が見られたら、専門業者による調査をおすすめします:
- 北面の壁に緑色や黒ずんだ部分が目立つ
- 触るとぬめりがある、または粉が手につく(チョーキング)
- 一部だけ塗膜が剥がれている・ふやけている
- 雨のあと、いつまでも乾かない箇所がある
- 軒下や基礎まわりに、原因不明の汚れがある
■ 日陰部の補修・再塗装のポイント
- 防カビ・防藻性の高い塗料を選ぶ
再塗装の際は、防カビ・防藻性能が高い塗料を選定することで、再発を防ぎやすくなります。
- 高圧洗浄と下地処理が重要
塗装前の洗浄工程で、しつこいカビやコケをしっかり除去することが長持ちのカギです。
必要に応じて、バイオ洗浄剤を使うのも効果的です。
- 通気・排水の見直しも検討
塗装だけでなく、換気不足や排水不良など構造的な原因がある場合は、
それらも一緒に見直すことでトラブルの再発防止につながります。
■ 補修タイミングの目安は?
日陰・北面の壁は、見た目では劣化が進行しているように見えにくいため、
築10年を超える場合や前回塗装から7〜10年経過している場合は、
一度専門業者に調査を依頼するのが安心です。
■ まとめ
日当たりの良い面と比べて、北面や日陰の壁面は「静かに、でも確実に」劣化が進みます。
特にカビやコケなどは早期対応が必要で、放置すると見えない部分の腐食や下地劣化を招くことも。
見えにくい場所ほど、定期点検とプロによる診断が重要です。
ぜひ、外壁全体の塗膜チェックの一環として、北側の壁にも目を向けてみてください。
4. 交通量の多い道路沿い
― 交通量の多い道路沿いの建物の場合 ―
幹線道路や産業道路、主要交差点に面した工場・倉庫・マンションは、
立地上、さまざまな環境負荷に常にさらされています。
特に塗装塗膜に関しては、通常よりも早く劣化が進行するリスクがあります。
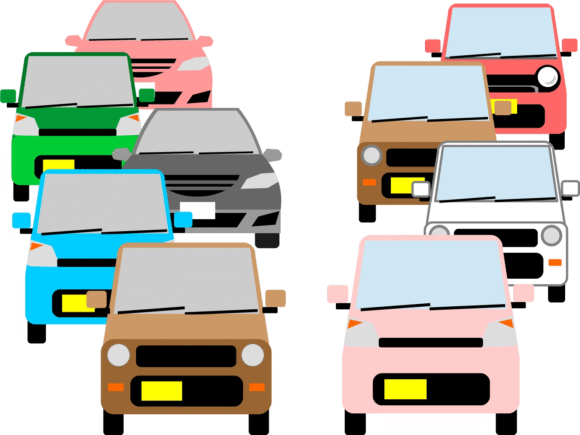
■ 道路沿い特有の塗膜劣化要因
・排気ガス・煤煙による化学的劣化
自動車の排ガスに含まれる**窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)**は、
塗膜に化学的ダメージを与え、表面の変色・劣化を促進させます。
・粉塵・ススの付着による汚れ・変色
交通量が多い場所では、建物表面に黒ずみ・くすみが短期間で付着。
美観を損ねるだけでなく、汚れが塗膜の劣化を早める要因にもなります。
・振動・風圧・乾湿繰り返しによる疲労
大型車両の走行による振動や、車道からの巻き上げ風・粉塵の影響も無視できません。
これらは、外壁や塗膜に対する微細なストレスとなり、経年で劣化が加速します。
■ よくある劣化症状(道路沿い立地で見られやすい)
|
症状 |
原因 |
対応の目安 |
|
表面の黒ずみ・黄ばみ |
排ガス・ススの付着 |
洗浄または早期再塗装 |
|
チョーキング(粉化) |
紫外線+化学反応 |
塗膜機能が失われているサイン |
|
塗膜のひび割れ |
蓄積疲労や微細な振動 |
下地劣化の可能性もある |
|
金属部のサビ |
粉塵+湿気+振動 |
早期対応が望ましい |
|
雨だれ・流れシミ |
排ガスや煤煙が雨と反応 |
防汚塗料で再発防止可能 |

■ 補修・塗替えの判断ポイント
交通量の多い立地では、一般的な塗膜の耐用年数より1〜3年ほど早く劣化が進むことも。
以下のタイミングでのチェック・再塗装が推奨されます。
- 前回塗装から 7〜10年以内(通常より早め)
- 建物前面(道路側)のみ汚れが顕著
- 美観重視の施設(店舗・マンションエントランスなど)で印象低下が心配
- 排気ガス汚れが拭いても落ちない
- 外壁の一部にサビや浮きが見られる
■ 対策・再塗装のポイント
- 低汚染・セルフクリーニング機能のある塗料を選ぶ
親水性塗料や光触媒塗料などは、雨で汚れを自然に洗い流す機能を持ち、道路沿いに最適です。
- 防錆・耐酸性に優れた塗料で金属部を補強
特にシャッターや手すり、看板フレームなどは、錆止め+高耐久塗装を選定しましょう。
- 道路側のみの部分塗装という選択肢も
全面塗装が難しい場合は、交通にさらされる面のみ重点的に施工することでコストを抑える手法もあります。
■ まとめ:見た目だけで判断しない補修の重要性
交通量の多い道路沿いにある建物は、見た目よりも内部の劣化が進んでいる可能性も。
単なる「汚れ」と見過ごさず、定期的な点検と早めの対応が大切です。
とくに第一印象が重要な施設・企業にとっては、清潔感ある外観維持が信頼感にもつながります。
5. 室内塗装(工場内・作業場等)
― 室内塗装(工場内・作業場など)の注意点 ―
塗装の劣化というと外壁や屋根の話と思われがちですが、工場や作業場の内部塗装も重要なメンテナンス項目のひとつです。
特に重機や化学薬品、粉塵などを扱う製造環境では、塗膜が受けるダメージは意外に大きく、
劣化を放置すると作業効率や安全性に悪影響を及ぼすこともあります。

■ 室内塗装の役割とは?
室内の塗膜には、以下のような機能があります:
- 美観の維持(清潔感・企業イメージ)
- 防塵・防錆・防カビなどの機能性
- 衛生管理(食品・薬品工場など)
- 安全表示(ライン・警告表示)
- 照明効率の向上(明色仕上げ)
特に工場や作業場では、機能性を目的とした塗装が多く、劣化するとその効果が大きく低下します。
■ 室内塗装の劣化症状と補修サイン
|
劣化症状 |
主な原因 |
補修の目安 |
|
塗膜のはがれ・浮き |
結露、衝撃、下地の劣化 |
周辺も含めて再塗装 |
|
床のすり減り・粉化 |
台車やフォークリフトの走行、重機設置 |
防塵塗装・エポキシ再施工 |
|
壁面の変色・汚れ |
油分、薬品、粉塵の付着 |
洗浄 or 上塗り |
|
カビ・腐食の発生 |
結露、換気不良 |
下地処理+防カビ塗料 |
|
安全ラインの消え・かすれ |
経年劣化・摩耗 |
再塗装またはマーキング補修 |

■ 室内塗装の補修時期の見極め方
以下のような状況に当てはまる場合、室内塗装の見直しや再施工を検討すべきタイミングです。
- 作業区域の床面がすり減り、粉が出るようになってきた
- ライン表示や注意表示が見えにくい・消えてきた
- 水気の多い場所で塗膜の膨れや剥がれが出ている
- 一部だけでなく、全体的にくすみや汚れが定着している
定期的な監査(HACCP、GMP、ISO等)で指摘対象になりやすい
■ 補修・再塗装の際のポイント
- 耐薬品性・防塵性のある塗料を選ぶ
作業内容に合わせて、エポキシ塗料・ウレタン塗料・水性塗料・無溶剤型などを選定。
- 床と壁で適した施工方法を分ける
床:防塵、耐摩耗、耐衝撃が求められるため、厚膜仕上げやコテ塗りも検討
壁・天井:防カビ・防汚・明色反射などを意識した塗装選定が重要
- 稼働中でも可能な部分施工や夜間施工の相談を
工場の稼働に影響しないよう、部分施工・休日施工・短工期対応が可能な業者選定もカギ。
■ まとめ:室内塗装も“見た目”だけで判断しない
室内の塗膜は、日差しや雨にさらされないため「長持ち」と思われがちですが、
実際には薬品・湿気・衝撃・摩耗などの複合的な負荷で、思っている以上に劣化が進行しています。
特に製造品質や作業環境の安全性が求められる施設では、
見た目以上に“機能性”が重要になります。
定期点検・塗膜診断とあわせて、室内塗装の更新時期のチェックをおすすめします。
✅劣化の見極めが資産価値を守る第一歩
塗装の劣化は見た目だけでなく、防水性や耐久性の低下、ひいては建物そのものの寿命にも影響します。
「まだ見た目は綺麗だから大丈夫」と油断せず、定期的な点検と早めの補修が、長期的にはコスト削減にもつながります。
点検や補修のご相談はお気軽に!
弊社では、現場環境や立地に応じた最適な塗装プランをご提案しています。
「これは劣化?」と気になる症状がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら
株式会社 植田
📞 0120-994-509(9:00〜18:00)
📧https://ueda-up.com/contact/
🏢京都市東山区福稲柿本町27番地-106
あなたの大切な建物を、もっと美しく、もっと長く使えるように。
私たちがそのお手伝いをさせていただきます。
小さな工事から一貫体制で最後までフォローいたします!