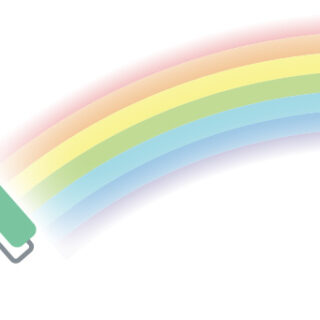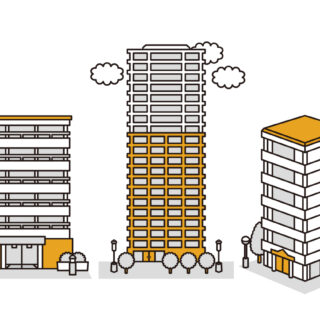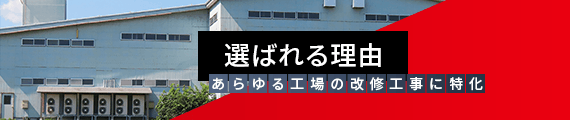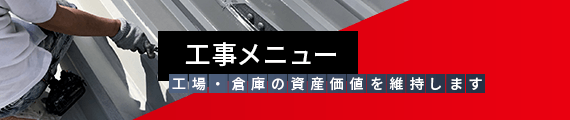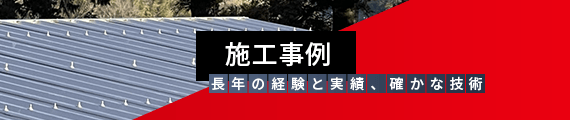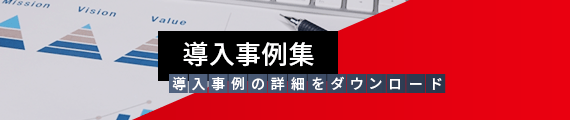工場改修の費用相場とコストダウンのポイント
老朽化や生産性向上のために工場改修を検討される企業は多いですが
「一体いくらかかるのか」「無駄なコストは省けるのか」といった疑問をお持ちではないでしょうか?
今回は、工場改修の費用相場と内訳、見積もりの見方、コストダウンの工夫、
助成金・補助金制度の活用のポイントなどを解説します。
改修費用の内訳とは?
工場改修には複数の工事項目が含まれており、それぞれに明確な役割と費用が発生します。
ここでは、主な内訳とその詳細を見ていきましょう。
● 足場工事費
高所での塗装や防水、外壁補修を行うためには仮設足場が必要不可欠です。
単価の目安:1㎡あたり800〜1,500円(外部足場の場合)
種類:クサビ式足場(一般的な低層建物向け)、枠組足場(中〜高層対応)、吊り足場(高所や危険箇所向け)
注意点:安全基準を満たすための設置が法律で義務付けられており、足場の撤去・搬出費も含まれるため、見積もりでは「足場一式」などにまとめられることが多いです。
● 外壁・屋根塗装
塗装工事は、工場の外観美観の維持はもちろん、金属やモルタルの劣化を防ぐ保護膜としての役割があります。
外壁塗装相場:1㎡あたり1,800〜3,500円
屋根塗装相場:1㎡あたり2,000〜4,000円
使用塗料の種類:ウレタン・シリコン・フッ素・無機など(耐候性と価格のバランスが異なる)
工法の違い:ローラー・吹き付け・刷毛などがあり、施工方法でも費用が変動します。
ポイント:金属外壁の場合は「サビ止め処理」「下塗り・中塗り・上塗りの3層仕上げ」が基本となり、それぞれの工程が明記されているか確認しましょう。
● 設備更新(空調・配管・電気など)
老朽化した設備は生産効率や安全性の低下につながります。更新費用は規模や機器によって大きく異なります。
空調設備:業務用エアコンや換気設備の更新で1台あたり30万〜150万円程度
電気設備:照明のLED化、分電盤の更新、非常用電源の設置など。内容により10万円〜数百万円の幅
配管設備:老朽化による水漏れやサビの防止対策として更新。配管ルートや距離によって数十万〜数百万まで幅があります。
ポイント:特定の設備更新は、省エネ補助金の対象になる場合があるため、事前に補助金制度を確認しましょう。
● 防水工事・床補修工事
工場の床や屋根からの雨水・油・薬品などの浸入を防ぐための施工が必要です。
ウレタン防水相場:1㎡あたり4,000〜7,000円(複雑な屋根形状や下地劣化があると上振れあり)
シート防水:ビル型工場の屋上などで使用。1㎡あたり5,000〜9,000円程度
床補修工事:コンクリートのクラック補修、耐薬品性塗床(エポキシ・ウレタンなど)など。
相場は㎡あたり2,500〜6,000円。
ポイント:防水工事は「下地処理」「プライマー塗布」「主剤塗布」「トップコート」と複数工程があるため、安価すぎる見積もりには注意が必要です。
● 諸経費・設計費・管理費
工事に直接関係しないように見えて、安全・品質・スムーズな工事進行に不可欠な費用です。
設計費:改修内容によって図面や仕様書の作成が必要。全体費用の3〜5%程度
現場管理費:工事監理、品質管理、安全管理のための人員や設備費。全体費用の5〜10%
諸経費:交通費、通信費、事務手数料、仮設トイレ・電源などの雑費を含む。
全体としては、諸経費・設計費・管理費を合わせて、工事総額の10〜20%程度が目安です。
■ 内訳を理解すれば、適正価格が見えてくる
見積もりを細かく見ていくと、「どこにお金がかかるのか」「何を削れるのか」「適正価格か」が見えてきます。
“一式”の項目が多い見積もりには注意し、できるだけ詳細内訳を出してもらうことが、予算管理の第一歩です。
見積もりの読み方と比較のコツ
工場改修では、見積書の内容をしっかり読み解く力がコスト削減の第一歩になります。
単に金額の多寡で判断せず、項目の内訳や工事の範囲、使われる材料や工法の違いまでチェックすることが重要です。
以下に、見積もりを読む際・比較する際の具体的なコツをご紹介します。
① 明細を細かく確認する
見積書には、「一式」や「〇〇工事一式」とまとめて書かれていることがあります。
しかし、この「一式」の中に何が含まれているのかを確認しないと、後で追加費用が発生する可能性もあります。
チェックポイント
● 材料費・施工費・搬入費・廃材処分費が分かれているか
● 仮設工事(足場・養生)や運搬費などの項目が含まれているか
● 工事ごとの数量・単価が明記されているか
例
| 工事項目 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 足場設置 | 1,000円/㎡ | 500㎡ | 500,000円 |
| 養生シート | 300円/㎡ | 500㎡ | 150,000円 |
このように、金額だけでなく、どのような数量と単価で積算されているかを見ることが、
見積りの妥当性を判断するカギになります。
② 相見積もりで金額差をチェック
複数の業者から見積もりを取ることで、相場感が把握できるだけでなく、コスト削減の交渉材料にもなります。
推奨は「最低2〜3社」
● 金額に差がある理由を確認する
● 明らかに安い・高い場合は、見積条件や仕様の違いがないか確認
● 業者の対応力・説明の分かりやすさも評価ポイント
注意点
● 同じ工事項目・数量での見積り比較が前提(依頼時に工事範囲や希望仕様を統一しておく)
● 金額の差だけで選ばず、実績・保証内容・工期の説明なども比較材料に入れましょう
③ 工事範囲の違いに注意
価格だけを見て判断すると、実は安い見積もりの方が施工範囲が狭かったり、使用する材料のグレードが落とされていることがあります。
よくある違い
● 塗装面積の算出方法(外壁の開口部を含むor除く)
● 使用塗料のグレード(シリコン vs フッ素 vs 無機)
● 工事に含まれる工程の有無(例:下地処理や高圧洗浄の省略)
対応策
● 「どこからどこまで施工してくれるのか」を必ず質問し、図面や現地写真などで確認
● 材料名や施工内容は、カタログや仕様書でグレードを確認するのが確実
例
A社:フッ素塗料(耐久年数15年)で塗装…3,000円/㎡
B社:シリコン塗料(耐久年数10年)で塗装…2,200円/㎡
→ 金額の差は塗料の性能差によるもので、長期的に見ればA社の方がコスパが高い可能性も。
■ 見積もりの「わからない」は放置しない
わからない専門用語や不明な項目があった場合は、遠慮なく業者に説明を求めることが大切です。
誠実な業者であれば、丁寧に回答してくれるはずですし、説明対応の姿勢も信頼できるかどうかの判断基準になります。
■見積書を“読む力”が、コスト管理力になる
工場改修は大きな投資です。見積書をしっかり読み解き、複数の業者を比較しながら工事範囲・内容・使用材料を見極めていくことが、コストパフォーマンスの高い改修の実現につながります。
無駄なコストを削減する工夫
工場改修では、見積もり金額を下げることだけが“節約”ではありません。
施工計画や材料選定、社内の協力体制などを工夫することで、品質を落とさずに総費用を抑える方法は多数あります。
以下のポイントを押さえることで、より効率的なコストダウンが可能になります。
改修範囲の優先順位をつける
すべてを一気に改修しようとすると費用が膨らみがちです。
そこで重要なのが、工場全体を調査したうえで、優先順位を明確にすることです。
優先順位の決め方
● 劣化が著しく、使用に支障が出ている箇所
● 雨漏れ・水漏れなどの緊急性が高いトラブル発生部位
● 法令・安全基準を満たさなくなる恐れがある部分
● 設備更新などで生産効率が大きく向上する部分
たとえば、外壁は一部クラック補修にとどめておき、来期に全面塗装を行うといった段階的な対応にすることで、
初期費用の負担を軽減できます。
ポイント
改修範囲に「必要性の高いゾーン」・「来年度対応ゾーン」などの優先マップを作成すると
業者との打ち合わせがスムーズです。
稼働停止期間の短縮
工事中にラインを止めたり、エリアを閉鎖すると、工事費以上の生産ロス=隠れたコストが発生します。
これを抑えるためには、施工計画そのものを工夫することが重要です。
工夫できるポイント
● 休日・夜間・長期休暇中の施工を提案
● エリア分割施工(工場を稼働させながら部分的に改修)
● 短工期の工法を選択(速乾塗料やプレカット材の活用)
例
● 防水工事を梅雨前の短期間で終える計画を立てる
● 床補修を稼働が少ない週末2日間に集中して実施
事前の綿密な工程打ち合わせが不可欠です。
「いつ・どこを・どの順で工事するか」のスケジュール調整に時間をかけることで、生産への影響を最小限に抑えられます。
長寿命材料の選定
「初期費用が安い材料」を選ぶと、短期間で劣化して再施工が必要になるケースがあります。
これはかえって総費用が増える原因になります。
考え方
● 長寿命の塗料(無機・フッ素系)や高耐久シート材を使用することで、ライフサイクルコスト(LCC)を削減
● 10年で再塗装が必要な塗料よりも、15年もつ塗料を選べば将来的な足場費用や施工費が1回分浮く可能性も
具体例
● ウレタン塗料(耐用年数約7〜10年)よりも、無機塗料(15〜20年)を選べば、再塗装の回数を半減
● 金属屋根の張替えでは、遮熱・断熱性能付きのガルバリウム鋼板を使用すれば省エネ効果も期待でき、
● 長期的な電気代削減に貢献
短期的な支出ではなく、10年・15年という視点で材料を選ぶことで、結果的にコストパフォーマンスが良くなります。
自社でできることは事前準備で対応
外注すべき工事と、自社で対応できる準備作業を切り分けることで、工事全体の効率が上がり、費用削減につながります。
自社対応で効果的な項目
● 施工エリアの片付け・備品の一時移動
● 書類準備や申請関連のサポート
● 工事内容の社内説明・共有(トラブル防止)
● 清掃作業や簡易な養生(場合により)
これにより、施工業者の現場作業時間が短縮され、人件費や工期を削減できます。
注意点
危険作業や専門知識が必要な作業は無理に対応せず、
業者と事前に「自社でできること/できないこと」の線引きをしておくことが大切です。
ちょっとした工夫で大きな差に
工場改修のコストは、単に「削る」のではなく、「見直す」「分ける」「先を見て選ぶ」「一緒に動く」ことで、
質を落とさずに無駄を省くことが可能です。
現場の事情や予算に合わせた最適な改修方法を、業者と一緒に設計していくことで、
納得感のあるコストダウンを実現できます。
助成金・補助金制度の活用方法(注意点と成功のポイント)
工場の改修工事では、国や自治体の助成金・補助金制度を利用することで、工事費用の一部をまかなえる可能性があります。
ただし、制度を利用するためにはいくつかの注意点と準備が必要です。
事前に理解しておくことで、スムーズな申請と活用が可能になります。
公募期間に注意する
補助金は通年で募集されているわけではなく、決められた期間にのみ受付される「公募制」です。
申請したいと考えた時にすでに締切が過ぎていることも珍しくありません。
対策
● 毎年の公募時期を事前に把握(例:春〜初夏に集中するケースが多い)
● 地元自治体や商工会議所のHPを定期的にチェック
● 気になる制度があれば、「次回募集はいつか」を問い合わせておく
申請から工事着工までの流れを理解しておく
補助金の多くは「交付決定通知が出てから工事を開始すること」が条件となっています。
つまり、申請前に工事を始めてしまうと補助対象外になるケースが大半です。
よくある失敗
● 見積書を準備して申請したつもりでも、「着工が早すぎて不採択」になる
● 工期がタイトで、補助金が間に合わず断念
対策
●「交付決定通知が出るまで工事は待つ」が原則
● 工期に余裕を持ってスケジュールを組む
● 早めに業者に相談し、「補助金ありきの施工計画」を立てる
申請書類の準備は早めに・丁寧に
助成金や補助金の申請には、事業計画書・工事内容の説明・見積書・収支予測・法人の決算書など、複数の書類が必要です。
一部でも不備があると不採択になる可能性があるため、申請書類の精度が非常に重要です。
対策
● 補助金に慣れている業者に書類作成をサポートしてもらう
● 専門の行政書士に相談するのも選択肢
● 書類準備は公募開始より前に着手しておくと安心
補助対象外の費用があることを理解する
すべての工事費用が補助金でカバーされるわけではありません。
制度によって、一部経費は対象外となる場合があります。
例(対象外になりやすいもの)
● 仮設トイレ・事務所設備などの間接費
● 工事と直接関係のない備品購入
● 補助金採択前に発生した費用(契約・着工・納品など)
対策
● 「どこまでが対象か」を必ず事前に確認
● 見積書も「補助対象経費」「対象外経費」に分けて整理してもらうと◎
採択されるとは限らない
補助金は申請すれば必ずもらえるわけではなく、採択審査があります。
書類の内容や予算の関係で不採択になることもあります。
対策
● 補助金ありきで工事を組むのではなく、採択されなくても実行できる計画にしておく
● 過去の採択事例や評価基準を研究し、実現性や地域貢献性を高める表現を意識する
事後の報告義務がある
補助金は「もらって終わり」ではありません。
多くの制度では、工事完了後に実績報告書や支出証明書類の提出が必要になります。
対策
● 工事中から「使った費用の記録」や「進捗写真」などを保存しておく
● 報告書作成も見越して、業者に施工写真や証明書類の提出を依頼しておく
補助金を使うには「計画力と連携力」がカギ
助成金・補助金制度を上手に活用すれば、工場改修のコストを大きく抑えることが可能です。
ただし、申請のタイミング・書類の精度・業者との連携・工期調整など、いくつものポイントを押さえる必要があります。
「もらえるかどうか」は準備次第。早めに動き、制度を理解しておくことで、確実に活用できる可能性が高まります。
賢く改修し、コストを最適化
工場改修は設備の延命だけでなく、生産効率の向上や安全性確保にもつながる重要な経営投資です。
しかしながら、「なんとなく全部直す」「業者任せにする」だけでは、本来不要なコストを支払ってしまう可能性もあります。
今回ご紹介したように、以下のポイントを押さえることで、無駄を省きながら、効果的で持続可能な改修計画が実現できます。
✔ 改修費用の内訳を理解し、予算配分を最適化
足場、塗装、設備更新、防水、設計・管理費など、見積もりの中身を把握することで過剰な支出を避けられます。
✔ 見積書は複数社で比較し、内容と工事範囲までチェック
「安い=お得」ではありません。仕様の違いや施工範囲も含めて比較することが大切です。
✔ 節約ではなく“賢い投資”で無駄なコストを削減
優先順位の設定、長寿命材料の採用、稼働停止リスクの低減など、全体最適の視点での判断が結果的にお得になります。
✔ 助成金・補助金制度の活用で公的支援を受ける
制度を活用すれば、最大で数百万円の支援を受けられる可能性も。公募時期や申請条件をしっかり確認しておきましょう。
最初の一歩は「信頼できる業者への相談」から
自社にとって本当に必要な改修内容は何か。
費用はどこまでかかるのか。
補助金は使えるのか。
これらを見極めるには、現地調査とヒアリングが欠かせません。
まずは実績のある専門業者に相談し、具体的な課題と優先順位を一緒に整理してもらうことからスタートしましょう。
そうすることで、無駄なく、安心して、効果の高い工場改修が実現できます。
弊社は、ご相談・お見積り無料でさせていただいておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ![]()