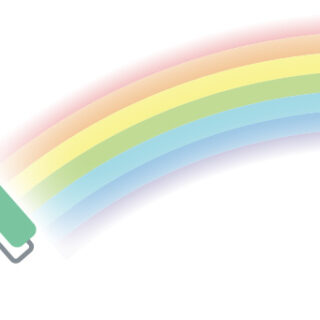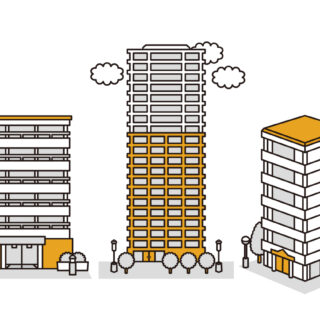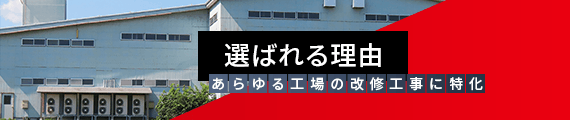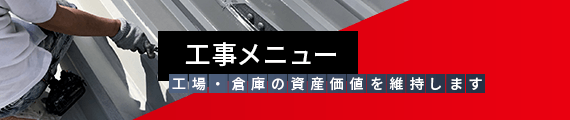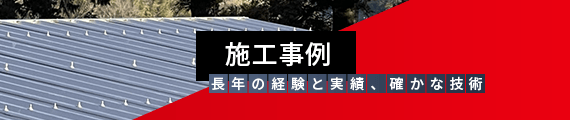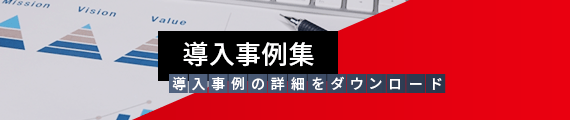工場の改修、何から始める? 準備の第一歩と知っておきたい基本知識
工場の改修を検討し始めたとき、「まず何をすればいいのか分からない」「改修に関する知識がなくて不安」
という企業担当者の方は多くいらっしゃいます。
今回は、工場改修をスムーズに進めるために、初期段階で知っておくべき基本情報と、企業側で準備しておくべきことを分かりやすく解説します。
工場改修とは? まず目的を明確にしましょう!!
工場改修とは、設備や建物の老朽化を防ぎ、生産効率や安全性、快適性を向上させるための工事です。
主な改修内容は以下の通りです
-
外壁・屋根の補修や塗装
-
配管・電気設備の更新
-
生産ラインのレイアウト変更
-
床や内装の改修
-
空調や断熱対策の強化
まず最初に大切なのは「なぜ改修を行いたいのか」という目的を明確にすることです。
たとえば以下のような目的が考えられます
-
老朽化による安全性の確保
-
エネルギー効率の改善(断熱・遮熱)
-
雨漏れ・カビの対策
-
作業環境の快適化・生産性の向上
目的が定まることで、工事の範囲や優先順位も見えやすくなります。
改修に向けて企業側で準備しておくべきこと
工場改修を成功させるには、事前準備がとても重要です。
以下は企業側でできる代表的な準備項目です。
①建物や設備の「現状把握」を丁寧に行う
まずは、今の工場の状態をしっかりと把握することから始めましょう。
■ 図面・仕様書・過去の工事履歴の整理
建物の竣工図や設計図面、仕様書などがあれば、業者とのやり取りがスムーズになります。
過去の補修履歴や改修工事の内容も分かるようにしておきましょう。
■ 劣化箇所・トラブルの洗い出し
建物や設備の中で、不具合や老朽化が目立つ部分を具体的にリストアップしておきます。
-
屋根の雨漏り
-
外壁のひび割れや塗膜の剥がれ
-
床や通路のひび割れ・段差
-
配管のサビや水漏れ
-
空調・電気設備の故障や異音
■ 現場の声を集める
日々現場で作業している従業員から、困っている点や使いづらい設備についてヒアリングしましょう。
実際に働いている人の声を拾うことで、現場に即した改修につながります。
② 改修の「優先順位」を明確にする
工場や事業所の建物・設備の改修工事を検討する際、「全部を一度に改修できれば理想」と思う方も多いでしょう。
しかし現実には、予算や工期の制約、稼働スケジュールとの兼ね合いから、
一度に全て対応するのは難しいケースがほとんどです。
だからこそ重要になるのが、「改修の優先順位」を明確にすることです。
なぜ優先順位の整理が重要なのか?
改修工事には、建物の老朽化や設備の不具合など目に見える課題だけでなく、
将来の稼働計画や働く人の安全性・快適性など、さまざまな要素が関わってきます。
改修の必要箇所が複数ある場合、どこから手を付けるべきかを判断しないまま工事を進めてしまうと、
以下のような問題が起こる可能性があります。
-
予算の使いどころを誤ってしまう
-
工事のやり直しが発生する
-
安全リスクを見過ごす
-
現場の作業環境が改善されないまま残る
こうしたリスクを避け、より合理的な判断をするためにも、「改修内容の優先順位付け」は非常に大切なプロセスです。
![]() 優先順位の整理方法|3つのカテゴリーで分類する
優先順位の整理方法|3つのカテゴリーで分類する![]()
改修箇所の優先順位を整理する際には、以下の3つのカテゴリに分けて考えると分かりやすくなります。
![]() 【早急に対応が必要な箇所】
【早急に対応が必要な箇所】
最優先で手を打つべき改修ポイント。放置するとリスクが高まる箇所です。
<具体例>
-
屋根や外壁の雨漏り(生産設備への浸水リスク)
-
外構の破損(フォークリフト走行に支障)
-
配管の水漏れ・ガス漏れ
-
電気系統のトラブルや照明不良
-
手すりや階段などの安全設備の不具合
<判断の目安>
-
日常業務に直接支障が出ているか
-
労働災害や火災などのリスクが高まっているか
-
法令や安全基準に抵触する可能性があるか
このカテゴリの工事は、稟議・予算が多少厳しくても優先的に実施するべきです。
![]() 【数年内に対応したい箇所】
【数年内に対応したい箇所】
すぐに問題はないが、中期的に見て手を打っておきたい改修項目です。
<具体例>
-
外壁塗装の劣化(見た目の印象や塗膜保護)
-
空調・換気設備の性能低下
-
エネルギー効率が悪い照明や機器の更新
-
古くなった設備の更新(部品供給の終了が近い)
<判断の目安>
-
今後のメンテナンス費用が増えると予想されるか
-
使用頻度は高いが致命的な不具合はないか
-
生産効率や作業環境の改善につながるか
これらは、来年度以降の計画に組み込みやすい工事です。予算編成の段階から想定しておくと、無理なく実施できます。
![]() 【今回は見送るが将来的に検討したい箇所】
【今回は見送るが将来的に検討したい箇所】
すぐの対応は不要だが、将来的な改善計画として温めておくと良い部分です。
<具体例>
-
倉庫の拡張や動線の再設計
-
生産ラインの再構築やレイアウト変更
-
バリアフリー化や作業環境改善
-
省エネ設備やIoT導入に関する計画
<判断の目安>
-
実現に向けた課題がまだ多い
-
社内の要望があるが緊急性は低い
-
中長期的な投資として検討したい内容
これらは構想段階での情報整理や、業者への相談・資料作成から始めるのがおすすめです。
優先順位を決める際の社内での連携ポイント
改修工事の計画は、現場任せにせず、複数部署が連携して検討することが大切です。
-
現場作業者からのヒアリング
実際に使用している人の声は、改善のヒントになります。 -
設備保全・管理部門との情報共有
劣化状況やメンテナンス履歴を正確に把握しましょう。 -
経理部門との予算調整
年度内にどこまで予算を確保できるかも重要な判断材料です。
③「予算の目安」をあらかじめ決めておく
工場の改修工事を検討する際、最も悩むのが「費用はどれくらいかかるのか?」という点ではないでしょうか。
実際の金額は現地調査や詳細な見積もりが必要ですが、事前にある程度の「予算の目安」を立てておくことで、業者との打ち合わせが格段にスムーズになります。
なぜ予算の目安が必要なのか?
改修工事の計画段階で予算の目安が立っていないと、以下のような課題が生じがちです。
-
業者からの提案が広すぎて選べない
-
高額な見積もりが出て初めて予算不足に気付く
-
社内稟議や予算申請のやり直しが発生する
-
工事範囲の調整に時間がかかり、着工が遅れる
逆に、あらかじめ「今年はこれくらいまで」「この部分だけに集中したい」などの目安があれば、
的を絞った提案が受けられ、全体の工程もスピーディーになります。
![]() 予算を立てる際の3つの基本ポイント
予算を立てる際の3つの基本ポイント![]()
![]() 毎年の修繕積立や予算枠を確認する
毎年の修繕積立や予算枠を確認する
工場や事業所によっては、毎年一定額の修繕・保全予算が設けられているケースがあります。
まずはその金額や、過去の工事履歴をもとに「今年使える上限額」を把握しましょう。
-
修繕積立金や保守予算の残高
-
前年度の工事費用との比較
-
過去の同規模工事の実績金額
この時点で、「今年は300万円まで」「500万円以内でおさめたい」といった基準ができるだけでも、計画立案がしやすくなります。
![]() 今年度と来年度で分けて考える
今年度と来年度で分けて考える
もし現在の予算で希望の範囲まで工事を実施するのが難しい場合は、1年で全てを終わらせる必要はありません。
あらかじめ2年〜3年に分けた中長期計画として工事を進める方法も有効です。
例えば・・・
-
今年度は「雨漏り修繕」や「防水工事」などの緊急対応部分
-
来年度は「外壁塗装」や「倉庫内レイアウト変更」など将来計画
このように優先順位と合わせて分割工事の方針を持つことで、費用を分散しつつ効率よく改善が図れます。
![]() 複数の業者から見積もりを取り、相場を把握する
複数の業者から見積もりを取り、相場を把握する
見積もりを取る前でも、概算費用の感覚を掴むことは可能です。
複数の施工業者にヒアリングや概算見積を依頼することで、市場相場や費用感の目安を把握しましょう。
-
同一内容で相見積もりを取る(仕様はできるだけ揃える)
-
相場が不明な場合は「㎡単価」や「日数単価」で質問する
-
過去に依頼した業者がいれば、その工事費用も参考にする
また、業者によっては複数の金額プラン(基本プラン・省コストプラン・グレードアッププラン)を提示してくれる場合もあるため、それぞれ比較するのも有効です。
「予算感」を伝えるときの注意点![]()
予算の上限を業者に伝える際には、「この金額を全て使う前提」ではなく、
“この範囲で最適な提案をしてほしい”というスタンスで伝えるのがポイントです。
例えば・・・
-
「〇〇万円以内で、できる範囲で優先順位を絞って提案してほしい」
-
「この部分はマストで、それ以外は予算次第で検討したい」
-
「予算オーバーになりそうなら2年計画で調整したい」
こうすることで、過剰な仕様や不要な工事の追加提案を避け、目的に沿った提案が受けやすくなります。
④ 工場の「稼働スケジュール」を確認する
工場内で行う改修工事は、屋根や外壁のような外部工事にとどまらず
配管・電気設備・床改修など、内部にまで影響が及ぶケースも多くあります。
もしスケジュール調整をせずに工事を進めると、以下のようなリスクが発生します。
-
生産ラインの停止による損失
-
作業員の動線が妨げられる
-
騒音や振動による業務効率の低下
-
火気作業による安全リスクや工場ルールとの衝突
こうしたリスクを回避するためにも、「いつ・どこで・どのような工事をするか」を、稼働スケジュールと照らし合わせて検討することが不可欠です。
工事に最適なタイミングとは?
スムーズに工事を進めるためには、工場の稼働にできるだけ影響を与えにくい時期を選ぶことがポイントです。
以下のようなタイミングが代表的です。
● 年末年始・GW・夏季休暇などの長期休暇
生産が完全に停止している時期であれば、大規模な工事も実施しやすく、騒音や通行制限なども問題になりにくくなります。
※注意点:長期休暇中は業者のスケジュールも混み合いやすいため、数ヶ月前からの予約・打ち合わせが必要です。
● 生産ラインの切り替え・点検時期
工場によっては、定期的にラインを停止して設備点検を行う期間があります。
このタイミングに合わせて工事を行うことで、生産への影響を最小限に抑えることが可能です。
-
年2回の定期保全タイミング
-
設備入れ替えの合間
-
メンテナンス週間との連携
● 閑散期(繁忙期を避けたタイミング)
工場によっては、製造スケジュールに波があります。
繁忙期を避け、比較的余裕のある時期に工事を組み込むことで、突発的なトラブルが起きても柔軟に対応できます。
-
受注数が落ち着く時期
-
シフト人員が多い月
-
製品切り替え前の準備期間など
工事前に確認しておくべき社内スケジュール
工事のタイミングを決める前に、以下の情報を社内で整理しておくことをおすすめします。
-
年間生産スケジュール(ライン停止の有無)
-
機械設備の点検・入替予定
-
各部門の繁忙期・閑散期
-
建物内の使用状況(事務所・倉庫・通路など)
これらの情報を事前に業者へ共有することで、より現場に配慮した施工計画を立ててもらうことが可能です。
工事中の安全対策もしっかりと
稼働中に工事を行う場合は、安全確保と作業動線の維持も大きなポイントになります。以下のような点を事前に確認・検討しておきましょう。
● 仮設通路・作業エリアの確保
工事エリア周辺では、安全柵・養生・仮設通路の設置が必要です。
作業員やフォークリフトが安全に通行できる動線を確保することが必須となります。
● 作業音・振動への配慮
特に室内作業や床・配管工事などでは、作業音や振動が他部署の業務に影響を与える可能性があります。
作業の時間帯を限定したり、音の出やすい工程を休日や早朝に振り分けるなどの工夫が求められます。
● 火気作業と社内ルールの整合
溶接やバーナー作業などの火気を伴う工事を行う際は、工場側で定められている火気使用許可・立会い・防火対策などのルールを業者と共有しておきましょう。
必要であれば、施工中の立会いや、近隣設備への防火養生も事前に計画することが重要です。
稼働を止めずに工事するための工夫とは?
優良な施工業者であれば、稼働を維持しながら行う工事のノウハウを多数持っています。
たとえば以下のような工法やスケジュール提案があります。
-
夜間・休日限定での施工
-
一部分ずつの区画施工(稼働エリアと工事エリアの完全分離)
-
養生・足場の工夫による稼働エリア保護
-
工事期間を長めに取る代わりに稼働維持を優先
事前の相談次第で、工場稼働を止めずに改修工事を進める選択肢が大きく広がります。
3. 工場改修の流れを知っておこう
実際の改修工事が始まるまでには、以下のようなステップがあります(※期間は目安です)
① 現地調査・ヒアリング
専門業者が現場を確認し、状況に応じた提案を行います。
![]() 注意点
注意点 ![]()
建物の図面や既存設備情報があるとスムーズです。
② 見積もり・提案書の確認
複数業者から相見積もりを取ることも可能です。
社内調整や内容確認に時間を要することもあります。
![]() 注意点
注意点![]()
内容に抜け漏れがないか、安すぎる見積もりには注意しましょう。
③ 工事内容・スケジュールの打ち合わせ
工期、作業内容、費用などの詳細を詰めていきます。
![]() 注意点
注意点 ![]()
稼働スケジュールとの整合性や、工事中の動線確保も確認を。
④ 契約・着工準備
契約後、足場や資材の手配、工程計画、近隣への配慮準備などに入ります。
![]() 注意点
注意点![]()
契約書の内容(支払条件や工事範囲など)をしっかり確認しましょう。
⑤ 工事開始・完了
規模によって異なります。安全管理と進捗確認をしながら工事を進めます。
![]() 注意点
注意点![]()
作業音・粉じん・臭気などの対策も要確認です。
⑥ 引き渡し・アフターケア
完了後の報告書の提出、仕上がり確認、必要に応じて今後のメンテナンス体制を確認します。
![]() 注意点
注意点![]()
竣工検査や保証書の内容確認を忘れずに。
完了後の報告書の提出、仕上がり確認、必要に応じて今後のメンテナンス体制を確認します
1日〜数日 竣工検査や保証書の内容確認を忘れずに
4. 改修に必要な知識を少しだけ身につけておく
<よく出てくる専門用語の簡単解説>
-
シーリング:外壁の隙間を埋めて水の侵入を防ぐ素材
-
カバー工法:既存の屋根や外壁を撤去せずに新しい材料を重ねる施工方法
-
断熱材・遮熱塗料:室内の温度管理を助け、空調効率を上げる材料や塗料
-
防水層:雨水の侵入を防ぐために屋上やバルコニーなどに施工される層
-
下地処理:塗装や補修の前に行う表面の清掃・補修作業
-
塗膜:塗装後に形成される塗料の層で、建材を保護する役割がある
-
足場:高所作業のために設置される仮設構造物
-
アスベスト:かつて建材に使われた有害物質で、改修時に処理が必要な場合がある
-
耐候性:紫外線や雨風など、屋外環境に耐える性能
-
施工計画書:工事内容・手順・安全対策などを記した書類
安全面の配慮も必要
-
工事期間中、作業員や従業員の安全確保が大切です
-
仮囲いや作業区域の区分けなど、業者との協力が必要になります
5. 最初の一歩は「相談」から
工場や倉庫などの改修工事を検討しはじめたとき、
「どこに相談すればいいのか?」
「費用感や工期はどのくらいなのか?」
「自分たちの要望は伝わるだろうか?」
と、さまざまな不安を抱えているご担当者様も多いのではないでしょうか。
ですが、そんな時こそ大切なのが——
まずは“相談してみること”です。
プロに現場を見てもらい、対話を通じて状況や要望を共有することで、
現実的な改善案・費用の目安・進め方のヒントが自然と見えてきます。
「まだ具体的な計画が固まっていないけど、見てもらいたい」
「まずは話を聞いてみたい」
そんなスタンスで構いません。
小さな相談から始めることが、改修成功の第一歩です。
工場改修の相談をスムーズに進めるための5つのポイント
「せっかく相談するなら、できるだけ有意義な時間にしたい」
そんな方のために、工事相談を有効に進めるためのポイントをご紹介します。
①あらかじめ目的や要望を整理しておく
最初の打ち合わせでは、業者側も「何をどこまで求められているのか」を知りたいと思っています。
整理しておくと良い項目例
-
現状の困りごと(例:雨漏り、通路が狭い、空調が効かない)
-
今回の改修で達成したいこと(例:老朽化対策、省エネ対応、動線改善など)
-
優先したい項目と、今回は見送りたい項目の整理
-
工事に使える予算の目安(ざっくりでOK)
こうした情報が事前にあると、相談時のやり取りがスムーズで的確な提案が受けやすくなります。
②現場の関係者と一緒に立ち会う
改修相談には、できるだけ現場の実情をよく知る担当者の同席をおすすめします。
たとえば:
-
生産ラインの責任者
⇒ 稼働スケジュールや設備の使用状況について説明できる -
施設・建物の保守担当者
⇒ 劣化箇所や過去の修繕履歴を把握している
「このラインは24時間稼働」「この部分は作業中立ち入りできない」など、
現場のリアルな制約がその場で共有できることで、より現実的な工事計画が立てられます。
③疑問点・不安点は遠慮なく質問する
工場改修には、専門用語や見慣れない工法・材料がつきものです。
「こんな初歩的なこと聞いていいのかな…」と遠慮せず、分からないことは積極的に質問しましょう。
聞いておくと良い例:
-
「この工事って何日くらいかかるの?」
-
「工場を止めずにできる方法はある?」
-
「この症状は放っておくとどうなる?」
-
「この工法とあの工法、何が違うの?」
信頼できる業者であれば、専門的な内容も丁寧に噛み砕いて説明してくれます。
④複数の業者に相談・相見積もりを取る
1社だけに相談するのではなく、2〜3社に話を聞いてみることで、以下のようなメリットがあります。
-
各社の提案内容や視点の違いが比較できる
-
価格の相場感がつかめる
-
担当者の対応力・柔軟性が見えてくる
特に工場改修では、工事の「やり方」に業者の個性が出ます。
ただ安いだけでなく、納得できる提案をしてくれる業者を見つけましょう。
⑤施工実績や資格の有無をチェックする
相談時には、業者がこれまでにどんな工場改修を手がけてきたかを確認することも大切です。
-
似た規模や用途の工場での改修経験があるか
-
建設業許可や資格(監理技術者、職長、安全衛生責任者など)があるか
-
現地調査時の対応が丁寧か、説明がわかりやすいか
経験豊富な業者であれば、想定外のリスクも含めた現実的で安全性の高い計画を立ててくれるはずです。
まずは「見てもらうだけ」でもOK!
「まだ改修するかどうか決まっていない」
「何を優先したらいいかわからない」
そんな段階でも、現地を一度見てもらうことで、考える材料が一気に増えます。
工場改修を成功させるために必要なのは、「完璧な計画」より「最初の一歩」です。
その第一歩が、“業者への相談”です。
実際に現場を見てもらい、要望を話すことで、方向性や優先順位、予算感が見えてきます。
相談のコツを押さえて、ぜひ一歩踏み出してみてください。
お困りごとがある方は、お気軽に私たちにご相談ください
当社でも、工場改修に関する「無料の現地調査・相談」を承っております。
-
現場の状況確認
-
お困りごとヒアリング
-
簡易的なアドバイスや方向性のご提案
など、ご相談だけでも大歓迎です![]()