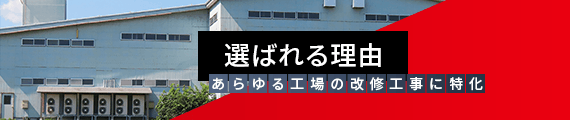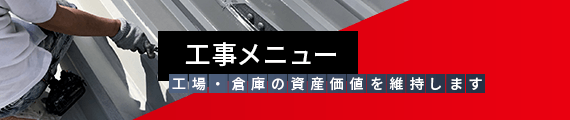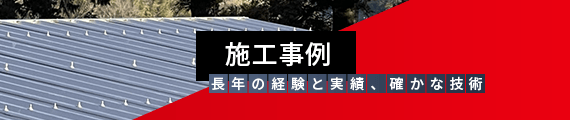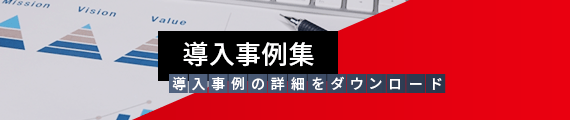補修工事における下地補修の重要性とは
工場・倉庫の補修工事において「下地補修」は非常に重要な工程です。
これは建物の安全性・耐久性・機能性を確保するうえで、まさに土台となる作業です。
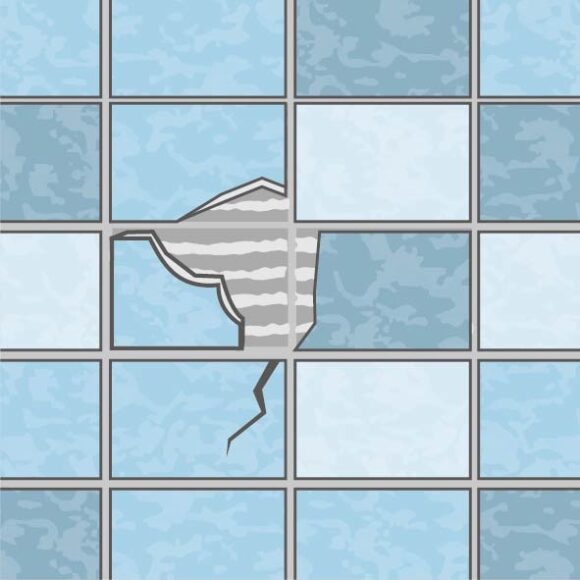
✅ 下地補修の重要性
- 建物の耐久性を維持・向上させる
下地(コンクリートや鉄骨など)が劣化している状態で上から塗装や防水工事を行っても、根本的な劣化は進行し続けます。
ひび割れ、欠損、鉄筋の露出などを放置すると、やがて建物全体の強度が落ち、重大な損傷に繋がる恐れがあります。
- 仕上げ工事の品質に直結する
塗装、防水、床の張り替えといった仕上げ工程は、下地の状態に大きく左右されます。
下地がデコボコだったり、水分を含んでいたりすると、仕上がりがムラになったり、すぐに剥がれてしまったりすることがあります。
- 工場・倉庫の機能性を維持
工場や倉庫では荷重・振動・温度変化などの影響を日々受けます。
床や壁のひび割れ・沈下などがあると、フォークリフトなどの機械がスムーズに使えなかったり、製品にホコリや水分が混入するリスクもあります。
下地を適切に補修することで、業務に支障が出るのを防ぎます。
- 長期的なメンテナンスコストの削減
初期段階で下地をきちんと直しておけば、その後の補修頻度や規模を抑えることができます。
結果的にトータルでのメンテナンスコストを抑えられるため、投資対効果も高くなります。
🔧 具体的な下地補修の例
🛠 屋根の補修
- ひび割れ・破損瓦の交換
- 棟板金の釘の打ち直し、シーリング補修
- コーキングの打ち直し(特にスレートや折板屋根)
- 金属屋根(折板・瓦棒屋根など)のサビ補修:
・ケレン作業(サビ除去:1種〜3種ケレン)
・サビ止め塗装(エポキシ系防錆プライマーなど)
・穴あきがある場合は鉄板パッチ補修 or ガルバリウム鋼板で部分張替え
原因:雨水・結露・塩害などによる腐食
目的:腐食の進行防止と防水材の密着性確保
- スレート屋根のひび割れ・欠損補修:
・クラック → ポリマーセメントや補修テープによる補修
・欠損部 → スレート差し替え or 金属板によるカバー補修
原因:経年劣化、荷重、地震など
注意点:古いスレートにはアスベストを含む可能性があるため、適切な処理が必要
- 屋根のビス浮き・金具の緩み補修:
・緩んだビスを打ち直し or ステンレスビスに交換
・ビス頭をシーリング処理で防水
原因:熱膨張・強風・経年変化など
目的:雨漏り防止・構造安定性の確保
- 屋根下地の腐食・劣化補修(下地合板、母屋など):
・腐った木下地の交換
・鉄骨母屋が腐食している場合 → 防錆処理・補強・交換
・下地合板の浮き → ビス止め再固定・張替え
原因:雨漏り・結露・排気ガス・老朽化
目的:屋根全体の強度と耐荷重性能の回復
- 屋根防水層の下地調整(塩ビ・ウレタン防水前):
・下地のひび割れや欠損を補修
・プライマー塗布 → レベリング材で平滑に調整
・ドレン周りの不陸(排水の勾配)も調整
目的:防水材の接着性確保、雨水処理の正常化
- 縁部・笠木・谷樋の下地補修:
・笠木下地や谷樋の継ぎ目からの雨水侵入を防ぐシーリング補修
・腐食した谷樋の板金交換
原因:雨水が集まりやすく、劣化しやすい部分
目的:屋根から壁・内部への雨漏り防止
🛠 屋上の補修
- 防水層の補修(ウレタン防水、FRP防水、シート防水など)
- クラックの補修:シーリング材やエポキシ樹脂で充填。
- 必要であれば防水層の再施工も検討。
🛠 外壁の補修
- 外壁のひび割れ(クラック)補修;
・幅0.3mm未満 → 微弾性フィラーや可とう性下地材で埋め戻し
・幅0.3mm以上 → Uカットシーリング材充填工法
・構造クラック → エポキシ樹脂注入による接着補修
外壁のひび割れ(クラック)の原因:地震、地盤沈下、温度変化、経年劣化、施工不良など
補修の目的:雨水侵入・錆・内部劣化の防止
- 浮き・剥離の補修(モルタル・タイル・ALC等):
・打診調査で浮き部分を確認
・浮いた部分を斫り(はつり)撤去
・樹脂モルタルで再成形・復旧
・必要に応じてアンカーピンニング工法を併用し固定
原因:下地との接着力低下、雨水浸入、経年など
目的:外壁材の落下防止、安全性確保
- 欠損・欠けの補修(ALCパネル・モルタル壁・RC壁など):
・欠損部を整形し、プライマー処理 → 樹脂モルタル等で復旧
・必要に応じて補強金具設置
原因:地震、機械接触、経年劣化
目的:防水性と強度の回復、美観維持
- シーリング(目地・サッシ周りなど)の打ち替え:
・古いシーリング材を完全に撤去
・プライマー塗布後に新しいシーリング材充填
原因:紫外線劣化、可塑剤の流出、硬化・ひび割れ
目的:防水性の確保、水の侵入による下地劣化防止
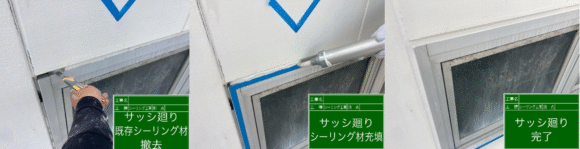
- 鉄部の錆・腐食部の補修(外部鉄骨、手すり、庇など)
・ケレン作業(手工具 or 電動工具でサビ除去)
・必要に応じて錆転換剤塗布 → 防錆下塗り → 上塗り仕上げ
目的:腐食拡大の防止、外観・安全性維持
- ALC外壁の中性化対策
・中性化検査(フェノールフタレイン試験など)
・状況に応じて中性化抑制剤の塗布やカーボネーション補修材使用
問題点:中性化が進むと鉄筋が錆びやすくなる
目的:鉄筋の腐食防止、建物寿命の延長
🛠 内部の補修
- コンクリート床のひび割れ補修(クラック補修):
・ヘアクラック → 低圧樹脂注入(エポキシ樹脂など)
・幅が広いクラック → Uカットシール材充填工法
原因:荷重や乾燥収縮、温度変化、経年劣化など
目的:水や油の浸入を防止し、床の強度を維持する
- 床の不陸調整・段差補修:
・セメント系自己流動モルタル(レベリング材)で不陸を平滑に調整
・エポキシモルタルなどで局所的な段差を修正
原因:沈下・ひび割れ・衝撃などによる変形
目的:フォークリフトの走行性・安全性の確保
- 爆裂(コンクリート内部の鉄筋が露出してサビている状態)の補修:
・剥がれた部分を斫(はつ)る
・防錆処理
・高強度のポリマーセメントモルタル等で復旧
原因:水分や塩分の侵入 → 鉄筋が錆びて膨張 → コンクリートが剥離
目的:構造耐力の回復、防錆対策
- 壁・柱の表面剥離や欠損部の補修:
・欠損部の清掃と接着剤塗布
・セメントモルタルや補修パテで再成形
原因:機械接触・荷物搬送・湿気や薬品の影響
目的:安全確保、見た目の回復、防塵対策
- 塗装下地の補修:
・ケレン(サビ・古い塗膜の除去)
・パテ処理や研磨での平滑化
・下地乾燥やプライマー塗布で密着性UP
目的:塗装の密着性を高めるための表面処理
- 床や壁の油染み・化学薬品染みの中和・除去:
・洗浄剤での油分除去
・酸・アルカリ中和処理
・吸着剤やセメント系素材で汚染部分の撤去と復旧
目的:新しい防塵塗装やコーティングの密着不良を防ぐ
📌 まとめ
補修工事における「下地補修」は、見た目だけでなく“構造の健康診断と治療”に相当します。
安全な工場・倉庫運営、快適な作業環境、資産価値の維持のためにも、軽視せず丁寧な対応が求められます。